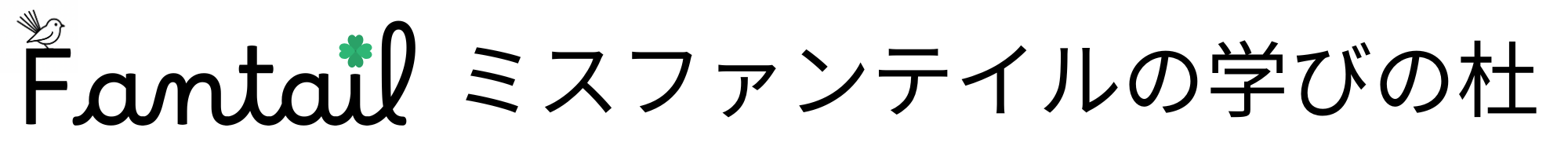子どもに習い事を始めさせる年齢や内容については、子どもの年齢が低いほど、親の価値観や願望が大きく影響します。親自身が「自分がやりたかったけど機会がなかった」「やってみたけれど続かなかった」など、親が実現できなかった夢を子どもに託すことが多いのも現実です。
何を、いつ始めるかの前に考えるべきこと
子どもの習い事において、親が最終的に何を求めているかを明確にすることはとても大切です。 子どもがプロになった姿を見たいのか、あくまで趣味として楽しんで欲しいのか、親としての目標をはっきりと意識することが必要です。多くの時間とお金を割いて、レッスンに通わせても、一定のレベルに達する前にやめてしまえば、スキルとして身に付くことはないでしょう。私の場合は、子どもがお友達と遊ぶときに不自由しないスキル(水泳、サッカー、テニス)と、高尚な趣味として生涯楽しめるスキル(楽器、言語)を身につけることが目標でした。前者は短期間で学べるスキルで、後者は時間をかけて長期間で育てるスキルです。多くのことを長期に渡って学ぶのは大変なので、成長するにつれて取捨選択を考えながら進めました。
子どもの適性を見極める
何が向いているかわからないので、子どもが小さいころには、様々な体験レッスンや見学に連れて行きました。武道、絵画、体操、バレエ、楽器、水泳、外国語、コーラスなど、できる限り多くのジャンルに触れさせ、興味のありそうなものは実際に通わせてみました。こうした体験を通じて、子どもの関心や適性を見極めることが重要だと感じたからです。興味があれば上達も早いですが、やる気がないと続けることが難しくなります。ですから、どの習い事が子どもに合っているのかを観察し、続けられるかどうかを見極めることが大切です。
子どもの能力を引き出せる先生を見つける
習い事を選ぶ際には、良い先生に出会うことが非常に重要です。体験レッスンや見学時に注意したいのは、先生が本当に子どもの能力を引き出し、伸ばしてくれるかどうかです。上手な先生が必ずしも良い先生とは限らないこともあります。例えば、プロのピアニストであっても、必ずしも子どもの成長を促せるかは分かりません。
私は、子どもが手を伸ばせば届くくらいの目標を設定してくれる先生を見つけることを重視していました。良い先生は、子どもの能力をしっかり見極め、がんばれば手の届く課題を与えてくれます。結果として、良い先生に出会うことで、子どもの能力が開花し、今でもその経験が役立っています。(学習者の能力を最大限引き出すための目標設定と教師選びについては以下のブログで詳しく書いています。)
習い事をやめるタイミングとその後の影響
習い事を長く続けることは難しいですが、どのタイミングでやめるかも大切です。例えば、ニュージーランドでは、泳げないと命に関わるとされているため、スイミングが非常に人気ですが、基本的には泳げるようになったらほとんどの子どもがレッスンをやめます。その他にも、サッカーやラグビー、テニスなど、シーズンによって違うスポーツをしたりする子どもも多く、長く続ける子どもは少ないようです。その時に楽しむためにやっているというような感じで、スキルを伸ばす目的ではなさそうです。
他には体操、バレエ、楽器などに熱中する人は多いですが、長く続ける人でも高校卒業までで終わる人が多いです。スポーツや音楽の習い事はやめると一気にレベルが落ちてしまい、元に戻すのが非常に難しいので、いつまで続けるのかは難しい決断です。もし「プロになれなかったらやめさせる」という考えなら、早い段階で子どもの適性を見極め、無理に続けさせない方が良いでしょう。しかし、子どもが楽しんでいるのであれば、プロを目指すという目的にこだわることなく、その時間を大切にしてあげてください。
思春期の子どもとお稽古
思春期に入ると、毎日練習することや、レッスンに行くこと自体が面倒になることがあります。学校や友達関係が忙しくなるため、習い事に対するモチベーションが下がることもあります。そういう時は、停滞期と思って子どものやる気が育つまで親は「待つ」しかないと思います。無駄なレッスン費を払い、送迎をすることにやるせなさを感じるかもしれませんが、実は子ども自身もどうすればいいのか、わからないのかもしれません。才能が溢れているのに、もったいない無いと思うのは親として当然ですが、説得したところでやる気がない時はやりません。私の場合は、喧嘩になりながらも、レッスンに通わせました。先生は一生懸命な方々だったので、子どもの知らないところで相談しながら、続けました。練習もしないで通ってくる無礼を許してくださった先生方には今も感謝しかありません。
親としての態度:子どもと共に成長する
親が「練習しなさい」と口を出すだけではなく、子どものしんどさを体験してみてはどうでしょう。私は、子どもに課題を与えられた際、自分も先に練習してから、子どもに教えるようにしていました。お母さんは「練習しなさい」と言うだけ、と言われる前に、私も苦しみを共有するため、子どもよりも先に課題を練習しました。そのおかげで、子どもが間違えて弾いているところにすぐ気づいたり、レッスンでの先生の注意点がよくわかるようになりました。何よりも、子どもが「辛いこと」が理解できるようになったのが良かったと思います。
さて、あなたのお子さんは、何を始めますか?
習い事を始めるかどうか、どの分野に進むかを決めるのは親ですが、最終的に子どもの意欲と適性に基づいて決めるようにしましょう。親の役割は、子どもの夢をサポートすることであり、無理に押し付けることではありません。子どもが自分のペースで、楽しみながら成長できる環境を提供することが、最も大切です。