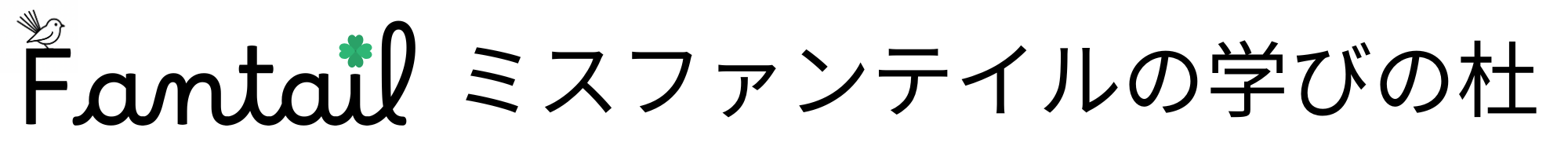幼少期に「本物」を使うことの意味とは?
小さい子どもには、ついプラスチックの食器や、壊れてもいい安価なおもちゃを与えていませんか?
「どうせ雑に扱うから」「高価なものを壊されたくないから」という大人の都合が理由かもしれません。
しかし、その裏には「子どもだから粗末なものでいい」という無意識の前提が隠れていることも多いものです。
私自身は、子どもが小さい頃から、なるべく大人と同じ“本物”を使わせるようにしてきました。理由は単純です。
「子どもだから粗末なものでいい」という考え方に、どうしても納得がいかなかったからです。
子どもに雑に扱っても構わないものを与えると、親も「まあいいか」と寛容になれるでしょう。子どもに注意することがないので、親のストレスも減るかもしれません。
しかし、それが習慣化すれば、子どもは「ものは壊してもいい」「汚しても大丈夫」という意識を自然と身につけてしまいます。
このように、小さい頃からものを粗末に扱い続けることに慣れてしまっていいのでしょうか?子どもたちはいつ「ものを大切にする心」を学ぶことができるのでしょう?
本物を使うことで育まれる感性と責任感
子どもに壊れやすい陶器の食器を使わせるのは危ない、という声もあるでしょう。
しかし、実際に壊れてしまうこともまた、大切な学びになります。
「叩くと割れる」「投げると壊れる」といった現実に触れることで、「どう扱えばいいか」を体で覚えていくのです。
私は、自分の子どもにも、陶器のお茶碗やティーカップを使わせていました。うっかりぶつけて、欠けてしまったこともありましたが、その時、子どもはとても残念な顔をしていました。そのたびに「どうして壊れたのか?」「どうしたら壊さずに使えるか?」ということを学んでいったと思います。その経験を通して、ものを大切に扱うことを覚えていきました。
小学生になった頃には、丈夫なマグカップよりも、口当たりの良い薄いティーカップを好んで使うようになり、大人と同様に繊細な食器も大切に扱うようになりました。「どんなことをしたら壊れるか」ということを、本人が理解していたからです。
もちろん、重すぎる食器や高級すぎる物は現実的ではありません。しかし、割れにくくて見た目にも上質な「コレール」などの食器は、子ども用としても非常におすすめです。
身の回りのものから育てる「大切にする心」
「ものを大切にする心」は、食器だけでなく、日常のさまざまな場面で育てることができます。
ある日、子どもと一緒に図書館で借りた本を読んでいたところ、ページが破れていたり、落書きがあったりするのを見つけました。子どもは驚いて、「なんでこんなことするの?」と聞いてきました。
私はそれをチャンスととらえ、「図書館の本はみんなで使うもの。だから大切にしないといけないね」「汚したり破いたりすると、次の人が困ってしまうよね」と伝えました。
また、音楽教育においても同様のことがありました。
私は自宅に古いアップライトピアノを持っていました。30年以上使い続けたピアノでしたが、とても大切に扱っていたおかげで状態が良く、引き取りの際には逆に査定額を付けて買い取ってもらえるほどでした。
子どもも、私がピアノを大切にしている姿を見ていたからか、自然とピアノを丁寧に扱うようになりました。
3歳の頃にはすでに「乱暴に扱うと壊れてしまう」という意識が芽生えていたようです。
その後、バイオリンを始めたときも、特に注意しなくても繊細なものを大切に扱う意識が定着していたと感じました。
大切なのは「高価なもの」ではなく「価値を伝えること」
ここで誤解してほしくないのは、「高価なものを与えるべき」と言いたいわけではないということです。
大切なのは、物の値段ではなく、「それが大切なものである」という価値を親がどう伝えるかという点です。
安価なものであっても、壊れやすいものであれば、大切に扱うべきです。
子どももそれを見て、「ものは大切にしよう」と思うようになります。
逆に、高価なものであっても、親が雑に扱えば、子どもも同じように扱います。
大切に扱うべきものを子どもに与え、私たち大人が、日常で物を大切に使う姿勢を見せることが、効果的な教育になるのです。
【まとめ】
「子どもだから粗末なものでいい」という考え方を、一度見直してみませんか?
”本物”を使わせることで、子どもは「ものを大切にする心」「丁寧に扱う感性」「責任感」を自然と育んでいきます。
高価なものでなくても構いません。
大切にすべき価値があるものを親子で共有し、その扱い方を一緒に学ぶことこそが、子どもの心を育てる教育です。