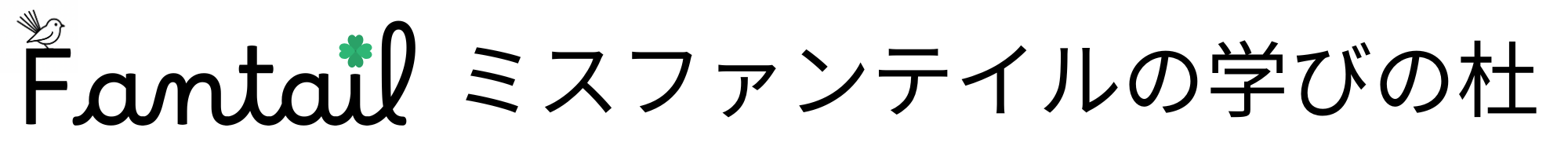生涯学習として何かを始めたいのだけれど、何を選べばいいのかわかりません。
A: 自分が何に興味があるか、考えてみましょう。まずは、以前にやったことがあることを伸ばしたいか、新しいことに挑戦したいか?次に、頭を使うことが好きか、手を使うことが好きか?これによって、語学学習、歴史研究、方言などの地域研究をやってみてもいいし、陶芸、書道、茶道などに挑戦してもいいと思います。何が好きかは、継続するのにとても重要です。楽しいことを見つけてください。
英語を話せないのですが、海外移住はできますか?
A: 新型コロナ感染症の流行前は、海外移住が流行っていたようですね。日本の厳しい夏や寒い冬を避けて、年間3ヶ月ぐらいを目安に海外に住んでいるシニアのご夫婦をよく見かけました。日本の海外旅行保険に加入している場合は、病院に行く時は無料で通訳サービスを受けることができたり、日本人の不動産仲介業者が住居を探してくれたりするので、英語ができなくても特に困ることはないかと思います。ただし、子どもがいる場合は、有料のサポートサービスもありますが、学校関係で英語がわからないと困る場面もあるでしょう。いずれにしても、英語ができないと家族ぐるみで付き合うような関係になることは難しいので、海外で住むことを楽しむという目的で一時的に住むのであれば良いか思います。
子どもにはネイティブの英語を学ばせたいが、どこの英語がいい?
A: 「子どもにネイティブの発音を身につけさせたい」という目的で、外国人教師を選ぶ保護者の方が多いようですね。しかし、英語には多くの種類のアクセント(発音の個性)があり、日本で講師をしている外国人講師の出身もさまざまで、英語が母国語でない方もいますが、保護者の方が気づいていないケースも多いかもしれません。せっかくネイティブスピーカーの先生に習っても、留学先の先生のアクセントが特殊なものだったり、仲良くなった家族が別のアクセントを持つ移民だったりと、成長途中で発音に影響を受ける機会が数多くあります。また、正直なところ、習った先生のアクセントが完全に身につくほど長い時間を共に過ごすわけではありません。それよりも、どこかのアクセントをマスターしていることよりも「通じる発音」を身につける方が重要だと思います。
胎教って本当に効果があるの?
A: 2歳ぐらいまでの子どもは、おなかの中にいた頃の記憶があると言われていますよね。私は、出産前に自分の父を亡くして毎日泣いてばかりいましたが、子どもが2歳になる前ぐらいに「おなかの中で何してたの?」と質問したところ、「暗かった」「ママ、ずっと泣いてた。」と言われ、なんと辛い思いをさせてしまったのだろうとショックを受けた記憶があります。
胎教にどのくらいの科学的根拠があるかはわかりませんが、命がものすごいスピードで育っていくわけですから、胎児も学習できるという考えが間違っているとは思えません。しかし、胎教で何か特別なことをするというよりも、赤ちゃんが生まれてから「見せたくないもの」「聞かせたくないこと」を避け、お母さんがたくさん話しかけてあげたり、音楽を聴いてゆったりと過ごすなど、楽しい経験をして幸せな気分で過ごしたりすることが、おなかの赤ちゃんに良い影響を与えるのではないか思います。また、お母さん自身が学びが赤ちゃんの学びにつながるのではないかと、私は考えています。
海外の子育てで大変なことは?
A: 日本語をネイティブレベルに身につけさせることだと思います。昔、アメリカで出会った日本人夫婦の子どもたちが、日本語に不自由しているのを知って以来、たとえ家庭で日本語しか使っていなくても日本語の読み書きを年齢相応レベルに身につけるのは難しいということを知りました。だから、私は自分の子どもの英語が伸び悩んでいる時も、日本語学習を優先していました。「英語の音を聞き取れる耳ができている限り、英語の遅れは必ず取り戻すことができる」と信じていました。結果的に英語も日本語も不自由なくできるようになりましたが、日本語を日々勉強させることは、本当に大変でした。