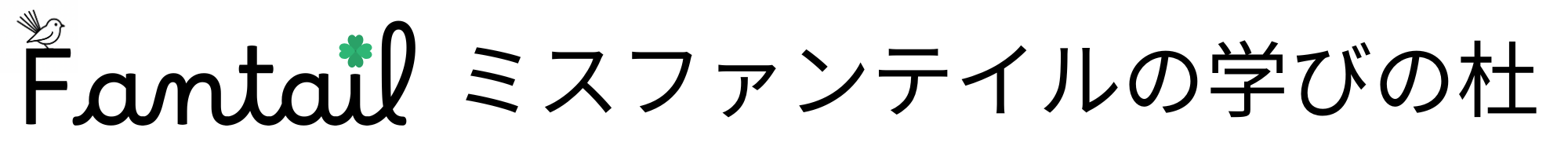これまで教育の現場で、発達障害、学習障害、適応の難しさなど、さまざまな個性や困難を抱えた生徒たちと出会ってきました。しかし、ある日、初めて出会ったのが「顔が覚えられない」という訴えでした。
記憶力の問題でも、不注意でもない。調べていくうちに、それは相貌失認(そうぼうしつにん)という脳の認知機能に関わる障害であることがわかりました。
この生徒との出会いは、私自身の教育観を大きく揺さぶる経験となりました。
相貌失認とは?──顔認識に特化した脳機能の障害
皆さんは、相貌失認という認知障害をご存知ですか?相貌失認は、英語では「Prosopagnosia(プロソパグノシア)」と呼ばれる認知障害で、顔だけを識別する能力に特化した脳の働きがうまく機能しないという特性です。馴染みのない疾患名ですが、日本語では「失顔症」とも訳され、人口の1〜5%に見られる可能性があると報告されています(『Cortex』2023年掲載論文、National Geographic日本版より)。実際に著名人の中にも、俳優のブラッド・ピット氏や神経学者のオリバー・サックス氏など、この症状を持つことを公表している人がいます。
「顔がわからない」という日常──生徒Aさんのケース
私が出会った生徒のAさんも、この相貌失認をもつ一人でした。最初に「顔が認識できない」と聞いたとき、私は意味を理解できませんでした。しかし、話を重ねるうちに、その困難の深さが少しずつ見えてきました。
Aさんは、目・鼻・口など顔のパーツ一つひとつは見分けられるのに、それを全体として「顔」として認識することができないのだそうです。人が多い場所では、家族の顔すら分からず、探し出すことができません。知っている人が近くにいても気づかない時もあり、「無視された」と誤解されることもあったそうです。
顔の代わりに「声」や「動き」で人を見分ける
人は目から入る情報を脳の中で再び立体化して作り上げて「モノを見る」そうですが、相貌失認は目から得た情報を脳で立体化するということに障害がある疾患のようです。Aさんは、顔を認識することができない代わりに、他の部分への認識力が非常に優れており、例えば髪の色、声、背の高さ、体型、仕草、などを細かく識別し、それらを統合して人を認識しているようでした。 私たちが無意識に顔で人を判別しているのと同じように、Aさんにとっては非顔情報が重要な手がかりになっていたのです。
相貌失認は発達障害と重なることも
Aさんの場合、相貌失認だけでなく、ADHD(注意欠如・多動症)、失読症(ディスレクシア)、書字障害(ディスグラフィア)といった複数の発達障害も併せ持っていました。顔がわからないという困難に加えて、文字を読む、書く、集中することにも困難があるという状況の中、Aさんは日々努力を重ねていました。
その姿を見て、「この子が顔がわからない世界でどれだけの苦労をしているのか」と想像するたびに、教室での当たり前の風景が違って見えるようになりました。
補足:私にも顔が覚えられない感覚が?
実はこの出来事をきっかけに、私自身の顔の記憶力について、ふと気づいたことがありました。それは、白人の顔、特に高齢者の顔が覚えづらくなっていることでした。「私も相貌失認なのかもしれない」と思いましたが、実はこれは「他人種効果(Other-Race Effect)」と呼ばれる別の現象であることがわかりました。
自分の属する人種以外の顔を見分けにくくなる傾向で、幼少期の経験や接触頻度に影響されます。相貌失認とは異なり、認知障害ではなく脳の学習と経験の差によるものです。
見えない困難に気づくために、教師にできること
Aさんとの出会いは、私にとって教育の視野を大きく広げる出来事でした。
教室で一見「普通」に見える生徒の中に、目に見えない困難や認知の特性を抱えている子がいること。教師がその困難を理解し、いかにサポートしてあげることができるかが問われていると思います。「顔が覚えられない」という症状一つ取っても、それがどれだけ日常生活に影響を与えるのか、どれだけ工夫が必要なのか 。
教育現場では、こうした認知の違いに敏感であること、柔軟であることが、多様な生徒たちの安心感と成長につながると、心から実感しています。
結びに:支援の第一歩は「知ること」から
相貌失認という障害を通じて、私は「見えない障害に気づく力」の大切さを学びました。教える側が、まず「知る」こと。それが支援の出発点であり、すべての生徒にとっての「安心して学べる場」への第一歩です。